井筒俊彦『アラビア哲学』(慶應義塾大学出版会)
かくて西暦一二〇四年に歿したユダヤ的アリストテレス哲学の巨匠マイモニデスに至るまで全てのユダヤ哲学書はアラビア語を以て著わされた。
十三世紀の西洋スコラ哲学、わけてもアルベルトゥス・マグヌス及びトマス・アクイナスの思想形成に甚大なる影響を及ぼせるユダヤ哲学思想なるものは、此等の翻訳が更にラテン語に訳されて西欧基督教界に導入されたものに他ならない。
基督教は起源的にはユダヤ教の一分派であり、回教はまたその本質上ユダヤ教と基督教との一分派であるから、両者いずれもかかるセム的予定観から本源的には自由ではあり得ない。
汪暉『近代中国思想の生成』(岩波書店)
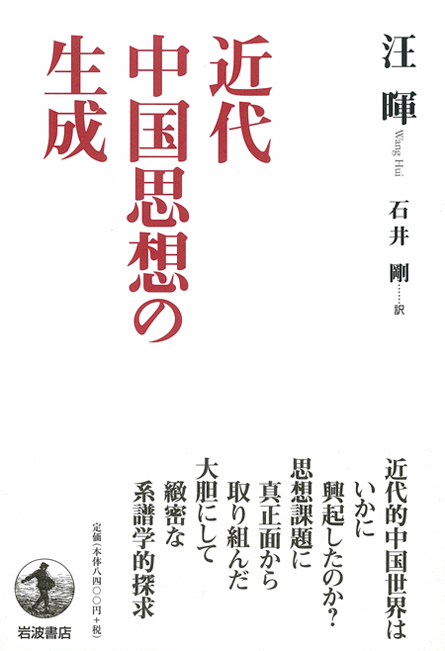
それは、「漢化」と「胡化」をめぐる論争に集中的に現れている。
「漢化」は、清末以降、中国史叙述における支配的モデルであった。だが、「新清史」研究者は、単一の、統一的な中国が古来から続く政治体であったと見ることに反対し、「征服王朝」やその固有のエスニック・アイデンティティに基づきながら、「漢化」としての中国観を批判する。
対立する双方ともが清朝の多元性を認めるが、前者は清代多民族国家が継続的な「漢化」プロセスを源として形成されてきた点を強調し、連続性という角度において、近代中国理解の基礎を得ようとする。
「漢化」というのは、清末民族主義に由来することばで、中国史上の民族融和現象について解釈する際に、その複雑で多面的なプロセスを過度に「漢」という概念に凝縮してしまっている。周知のとおり、「漢」という概念は本来種族概念ではなかった。
こうした背景の下で、「漢化」概念によって屈折を経た中国概念は、「中国」というカテゴリーが歴史的に遂げた変異や、内的な多元性を薄めてしまっている。
わたし自身は、「漢化」概念の代わりに「中国化」という概念を用いることにどちらかというと賛成だ。
こうしたアイデンティティの求め方は主体的なものであり、「漢化」という受動的な概念による説明はなじまない。
本書の訳者である石井剛さん、そして翻訳作業を企画してくださった村田雄二郎さんには心から感謝したい。
例えば、ジョヴァンニ・アリギは、ブローデルの長期的持続としての歴史叙述から影響を受けている。アリギは、金融資本はレーニンやヒルファーディングが考えたような世界的資本主義のある特定の段階ではなく、長期的に存在し、繰り返し現れる歴史現象だと述べている。
石井剛「訳者解説」
日本国内では、汪暉が村田雄二郎(東京大学大学院総合文化研究科)の招きで来訪し、二〇〇五年一〇月から半年、東京大学駒場キャンパスで一学期間にわたる大学院生向けの講義を担当した。
その後、村田が中心となり、日本語で最初の単行本となる『思想空間としての現代中国』(村田雄二郎・砂山幸雄・小野寺史郎訳、岩波書店、二〇〇六年)が刊行され、『生成』収録の附録(「地方形式・方言と抗日戦争時代における「民族形式」論争〔方言土語与抗日戦争時期”民族形式”的論争〕」、「アジア・イメージの系譜〔亜洲想像的譜系〕」。
もともとわたしが本書の訳出に取り組むことになったのは、村田雄二郎氏からの慫慂による。二〇〇八年四月、現在の職場に赴任したばかりのわたしを、ご自身の研究室に招いてくれた村田氏が、その場で岩波書店の馬場公彦氏とともに、この浩瀚な著作の翻訳について具体的なプランを明かされたのだった。現代中国研究を専門とはしていないわたしに白羽の矢が立ったのは、前述の駒場における汪暉の連続講義に、わたしが部外者であるにもかかわらず、毎回出席し、ときにぶしつけな質問を彼に浴びせていた図々しさに対して、きちんと学費を払いなさい、という村田氏(この講義のオーガナイザーであった)からの宿題であったと思っている。
度重なるぶしつけな質問に根気よく答えてくれた汪暉、本書に訳出を勧めてくれた村田氏、大きな度量で編集にあたってくださった馬場氏に感謝したい。
本稿の執筆にあたっては、草稿の段階で尾崎文昭、村田雄二郎、林少陽、王前、ヴィレーン・ムーティーの各氏から貴重なコメントをいくつも賜った。とりわけ、尾崎氏からは『学人』運動の当事者として、詳細なご意見を賜った。
汪暉自身は、天安門広場での民主化運動に参加していたことに対する懲罰措置として、農村に送られていわゆる「再教育」を受ける。
つまり、出版資金を提供した高筒光義、高橋信幸、そして、彼らと『学人』同人たちを仲介した中国人文学研究者たち(伊藤虎丸、尾崎文昭、窪田忍ら)である。
ここ二〇年来の、サンスクリットに関する、そしてヨーロッパ語とサンスクリットとの関連に関する発見は、まことに歴史上の一大発見であった。それはまるで新世界を発見したかのようである。とりわけ、ゲルマンとインド民族との関連は、ある種の見方を、こうした資料の中から最大限の確実性を得ることの可能なある種の見方を示している。今日に至っても、いくつかの民族はまだ社会を形成しておらず、ましてや国家の形成など言うべくもないのだということをわたしたちは知っている。しかし、それらの民族はとっくにそのようなものとして存在していたのだ。(中略)先ほど述べたような遠く離れたところの諸民族は、言語的にはつながりを有している。わたしたちの前には一つの結果が横たわっている。いわゆるアジアとは一つの中心点であり、諸民族はそこから分散していったのであり、もともと関連のあったものがかくも異なった発展を経ることになったということは、争うことのない事実である。
世界史において、「精神の理念」は、その現実性の中において現れる。それは一連の外部的形態であり、それらの形態のひとつひとつは現実に存在している民族であることを自ら名乗っている。しかし、そうした現実的な存在の側面は、自然的存在のあり方においては、「時間」の範疇にも、「空間」の範疇にも属している。
世界史は「東洋」から「西洋」へ向かう。なぜならヨーロッパは絶対的な歴史の終着点であり、アジアは起点なのだから。(中略)歴史には決定的な「東洋」がある。それこそはアジアだ。(中略)東洋はいにしえから今日に至るまで、「一人」だけが自由であることを知っている。ギリシャとローマの世界は、「何人か」は自由であることを知っている。ゲルマン世界は「すべて」が自由であることを知っているのだ。したがって、わたしたちが歴史の中に見出す最初の形式は専制政体であり、二つ目は民主政体と貴族政体であり、三番目は君主政体なのだ。
ヘーゲル『法の哲学 II』(藤野渉・赤沢正敏訳、中央公論新社)
利己的目的は、普遍性による制約を受けつつ実現される中で、あらゆる面で相互依存的な制度をうち立てる。個人の生活と福祉や、その法的現存在は、多くの人々の生活、福祉、権利と一緒に織り込まれている。それらは、こうした制度の上にしか存在せず、しかも、これらの関連の中でのみ現実的で頼れるものとなる。これらの制度は、さしあたって外的国家、つまり、必要かつ悟性的な国家であると見なすことができる。
こうして、産業は利潤を追求すると同時に、自らを営利よりも上に置くのである。それはもはや泥の塊や、範囲の限定された市民生活に固執することもなく、市民生活の享楽や欲望をむさぼろうともしない。それらの代わりに、流動性とか、危険とか破壊といった要素がもたらされる。さらには、利潤追求によって、産業は各地を結びつける最大の媒介物〔つまり海洋〕を通じて、はるか遠くの国と交易を行う。これは、契約制度を採用した法的関係である。同時に、こうした交易は文化交流の最も強力な手段であり、商業はこれを通じることによっても世界史的意義を獲得するのだ。