統制的/構成的
『デリダ 政治的なものの時代へ』(岩波書店)
チャー「デモクラシーの時ならぬ秘密」
このような実践的理念をはたしてカント用語で言う「統制的」と厳密にみなすことができるかどうかは議論の余地がある。というのも、カントにおいては、統制的/構成的という区別は理論に関する原理についてのみ言われているからである。「統制的」という言葉は、「統制的行動」というもっと控えめな意味しかもたないのかもしれない。「統制的」や「理念」という言葉のカントの用い方については、アレン・ウッドとギョルジー・マーカスとの議論から多くを得た。
カントの見解が第二批判書以後に変化したということ、またその後、カントは永遠平和や最高善といった理念を実現可能なもの、あるいは少なくとも目標――それらが不可能だということが証明されないかぎり、私たちが理性的に追求しなければならない目標――として見ていたということ、この点の論証については、それぞれ、Gyorgy Markus, "The Hope to Be Free: Freedom as Fact, Postulate and Regulative Idea in Kant," in From Liberal Values to Democratic Transition: Essays in Honor of Janos Kis, ed. Ronald Dworkin (Central European University Press, 2004). pp. 79-106とPaul Guyer, "Nature, Morality, and the Possibility of Peace," in Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge University Press, 2000), pp. 425-434を参照のこと。もし実践的理念が実現可能だとすると、「統制的」という用語は意味の激烈な変化を被ることになるだろう。
ゲルラク「赦しの脆さ」
すなわち、あたかも過去が決して生起しなかったかのように過去を一掃しようと試み、その結果、抑圧されたものが反復として回帰する危機を生み出す、そうした抑圧あるいは否認の様式における忘却である。
ランシエール「デモクラシーは到来すべきものか?」
実はあのくだりで彼が却下したがっているのは、来たるべきデモクラシーとカントの統制的理念との同一視である。彼が提示する第一の論拠は、来たるべきデモクラシーは今ここで活動しなくてはならないのだから、それは統制的理念ではありえないというものである。
それゆえに、その直後に来る第二の論拠は計算する機械という論拠になるわけだが、もちろんカントの統制的理念は、自動的な結果をもたらすために「穏やかに」適用されるだけの知という発想を含むものではない。
だからこそデリダは、規定的な判断ばかりではなく統制的理念をも、または《理性の命法》による倫理主体の自己規定をも、また場合によっては、美的な〈あたかも……であるかのように〉――私が言いたいのは、美的判断の〈あたかも……であるかのように〉によって新しい共通感覚を先取りするということである――をも、一緒くたにしてしまうのである。

ジャック・デリダ "Faith and Knowledge: The Two Sources of 'Religion' at the Limits of Reason Alone"
「信仰と知――たんなる理性の限界内における「宗教」の二源泉」松葉祥一・榊原竜哉訳、
『批評空間II』一一―一四号、一九九六―九七年
ジャック・デリダ "Given Time―I. Counterfeit Money"『時間を与える』
贈与があるためには、いかなる相互性もあってはならない。
[贈与は]自分自身を不可能事として告知し、不可能事として思考されるべくみずからを与える。
贈与は――仮にそうしたものがあるとすればだが――間違いなく経済と関連づけられるだろう。贈与を扱おうとすれば、経済とのこうした繫がりを――貨幣経済との繫がりをさえ――扱わないわけにはいかない。
しかし贈与はまた経済を中断するものでもあるのではないか(仮に贈与なるものがあるとすればだが)。経済的な計算を宙づりにすることによって、もはや交換を引き起こさないようなものでもあるのではないか。
贈与があるとすれば、贈与において贈られるもの(贈られる品物であれ、贈る行為そのものであれ、とにかくひとが贈るところのもの)は、贈与へ(性急に主体へとか、寄贈者へとか言わないようにしよう)帰ってはならない。贈与は循環してはならず、交換されてはならない。贈与はそれが贈与であるかぎり、いかなる場合も交換のプロセスによって、出発点への回帰という形での円の円環運動によって汲み尽されてはならない。
贈与が贈与として現われるや、あるいは贈与が贈与として自己自身を意味するようになるや、贈与は円環の経済的オデュッセイアのなかで無に帰されるとすれば、もはやいかなる「贈与の論理」もないし、そしてひとは、贈与についての整合的な言説は不可能になる、と言って安心するかもしれない。贈与についての言説はその対象を取り逃し、結局のところ、いつでも別の何かについて語るのだ、と。マルセル・モースの『贈与論』のような記念碑的な作品は、贈与以外のことについてあれこれと語っている、とそう言うところまで行くかもしれない。それは経済、交換、契約(do ut des)を扱っており、賭金の競り上げや供犠や贈与や対抗贈与について語っている。――要するに、事物そのものにおいて贈与と同時に贈与の無化をも強いるあらゆることについて語っている。
モースは贈与と交換の両立不可能性について、あるいは交換された贈り物は単なるお返しでしかないという事実について、十分に悩んでいない。
贈与の真理は非贈与に等しい、あるいは贈与の非真理に等しい。
贈与があるためには、受贈者は返礼の贈り物をしてはならず、償還しては、返済しては、負債を返してはならず、契約関係に入ってはならない、また受贈者は負債契約を交わしたのであっては絶対にならない。
贈与が与えられる[原語はであり、文字通りには「みずからを与える」]条件として、この忘却は受贈者の側においてだけでなく、まず第一に(まず第一に、とここで言うことができるならばだが)贈与者の側において、徹底したものでなければならない。贈与は支払われてはならないばかりではなく記憶に留められてもならず、犠牲の象徴として、象徴的なもの一般として保持されてもならないが、それはまさしく贈与「主体」の側においても当てはまるのだ。
実は贈与は、贈与者(それが個人主体であれ集団主体であれ)にとって、意識の上でも無意識の上でも、贈与として現われたり贈与を意味してはならない。贈与は、それが贈与として、そのようなものとして、それがそうであるところのものとして、その現象と意味と本質において現れるやいなや、象徴的・供犠的・経済的構造のなかに巻き込まれてしまうものであり、この構造は贈与を負債の儀礼的円環のなかで無に帰してしまうのである。
主体としての主体は決して贈与することもないし、贈り物を受け取ることもない。
主体と客体は贈与が拿捕された結果であり、贈与の拿捕である。
単に贈与の意図があるだけで、すぐさま善意や気前よさといった満足を与えるイメージを自己自身に送り返す。贈与する存在は自分自身を贈与者と知ることによって、自分自身を円環的・反射的な仕方で、一種の自己認知、自己承認、ナルシス的感謝において認識するのである。
贈与の条件を満たすような贈与とはいかなるものか。つまり贈与として現れることなく、また贈与として存在も実存もせず、意味も言わんとすることもない、そうした条件を満たす贈与とは、いかなるものか。欲望なき贈与、言わんと欲することのない贈与、非意味的な贈与、贈与の意図なき贈与とは? このようなものを、なぜ我々はまだ贈与と呼ぶのか。
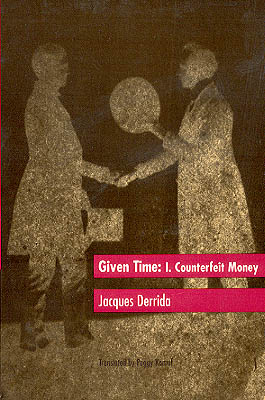
マルセル・モース "The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies"
『贈与論』(吉田禎吾・江川純一訳、ちくま学芸文庫)
しかしそれはある物を与えることが自己自身を与えることでもあるからであり、そして人が自己自身を与えるのは、人が自己自身を――その人の人格および財を――他者に「負う」からである。

